余震観測班速報
佐藤魂夫・Jim Mori・根岸弘明・R.P. Singh
諸機関の速報結果によれば、2001年1月26日インド西部Gujarat州に発生した地震のメカニズムは南北に最大圧縮軸を持つ逆断層型である。しかし、今回の調査計画を立ち上げようとしていた当初、地震断層は地表で観察されておらず、既存の活断層との関連は不明であった。また、本震メカニズム解のどちらの節面が断層であるかを示すような余震分布もどこからも公表されていなかった。このような状況において余震観測班は、詳細な余震分布から本震断層の位置、大きさおよび形状を決定することを主な目的として、現地で臨時の余震観測を実施することになった。
本震の発生からほぼひと月が経過した2月25日の昼に成田を出発し、夕方、Delhiに到着。Delhiではインド側の共同研究者であるカンプール工科大学(IIT, Kanpur)のR.P.
Singh教授、および余震観測への協力を買って出てくれたInstitute of Wadia Himalayan GeologyのSushil Kumar博士と合流した。翌朝、空路でGujarat州のAhmedabadに向かい、Ahmedabadからは総勢15人(カンプール工科大学の学生を含む)が3台の車に分乗して震源地を目指して移動した。AhmedabadからBhujまでは直線にして約300kmも離れており、夕方ようやくBhujの東約70kmにあるBhachauの町に到着した(図1)。先発のGPS班からBhachauの南西約40kmにあるGandhidhamでは開業しているホテルがあるという報告を受けていたが、Bhachauに到着した頃あたりはすでに暗くなり始めていたため、Bhachauで野営の場所を探すことにした。幸い、事情を説明するとGujarat州の警察が駐在していたキャンプ地に滞在を許され、翌日からはそのキャンプ地を基地として余震観測点の設置作業を行うことになった。
日本からは8観測点分の余震観測機材を持ち込んでいた。当然、観測点の配置は精度良く余震の震源決定ができることを念頭に考えられたが、余震域の広がりが明らかではない状況において8観測点をいかに配置するかは頭を悩ませる問題であった。結局、当初、地震のマグニチュードから東西100kmにも広がっていることが予想された余震域全体を8観測点で覆うことは、余震の震源を精度良く決定するためには得策ではないとの判断に立ち、余震域の東側半分の領域を占めると推測されたBhachauからRaparにかけての東西40kmの領域に重点的に展開することにした(観測点の配置図はhttp://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~tamao/India.htmlを参照)。地震計そのものはバッテリーで長時間作動するタイプなので場所を選ばないが、保安上、地震計の見張りを頼めそうな民家の近くを探した。しかし、Bhachauの観測点では近くに民家がなく、たまたま通りがかった農夫に頼んで、1週間、地震計の傍で寝泊まりをして見張りをしてもらうことになった。いずれの観測点においても住民の対応は協力的で、設置作業の途中でご馳走になったチャイ(ミルク入り紅茶)の味は格別であった。換震器は8観測点の半分が岩盤上、残りの半分がコンクリートの床の上に設置された。観測点の設置は27〜28日の2日間で終了し、観測は3月6日まで継続された。本震から1ヶ月が経過して、有感の余震回数はかなり減っていたが、時たま感じる有感地震によって我々は震源域の真上にいるという実感を得た。出発前、どうなることかとあれこれ心配したが、終ってみるとそれらは全くの杞憂で、概ね事は順調に運んだ。これはひとえにインド側の共同研究者、Singh教授およびKumar博士の協力のお陰であった。写真1はBhachauのキャンプ地を離れる際に撮った集合写真である。
観測点の設置を終了した翌日の3月1日、BhujでMemphis大学のCenter for Earthquake Research and Information (CERI)のRydelek博士に会い、彼らの余震観測の状況について話を聞くことができた。CERIの調査隊は2月11日から観測を始めていたが、前日の2月28日に観測を終了し帰国の荷造りをしているところであった。図はなかったが、予備的な結果から判断すると余震の面は南に傾斜しており、その面を延長すると23.8°N付近で地表と交差するとのことであった。Rydelek博士と別れたあと、我々はすぐに地震研究所の平田氏にこのことを報告し、すでに現地入りしているはずの地表地震断層調査班にも伝えてくれるようお願いした。当時、まだ地表でこの地震の断層は確認されておらず、こうした情報が日本の調査チームによる断層発見に役立つのではと考えられたからである。
観測期間中行動を共にしたSingh教授やKumar博士とは観測が終了した翌日の3月7日にBhujで別れ、我々はBhujからインド亜大陸の中央部に位置するHyderabadへ移動した。インド地球物理学研究所(NGRI)に立ち寄り、2月の上旬から震源域で臨時の余震観測をしているRastogi博士との情報交換が目的であった。彼は我々に2月7日〜15日に発生した余震の震源分布を見せてくれた。それによると、余震はBhujの近くにはほとんどなく、多くはBhujとBhachauのちょうど中間地点あたりから東側に分布していた。出発前、日本のマスコミではBhujの被害が大きく報道され、そのためBhujは震源域の直上にあると想像していた我々にとっては意外な感じがした。一方、余震はBhachauの近辺で数多く発生しており、我々が配置した観測網がその余震発生域を含んでいることを知ってほっとした。深さの断面を見ると、多くの余震は深さ15〜30kmに分布しており、10kmより浅い余震は数個しかなかった。余震は団子状に分布しており、どちらに傾斜しているかすぐには判断しかねた。CERIおよびNGRIの予備的な結果を見聞きし、我々は今回の地震は10km〜30kmと地殻の深い部分がすべり、その結果地表に断層が出現しなかったという印象を持った。なぜ、深い地殻の下部でこのような大地震が発生するのだろうか。インド亜大陸のプレート内地震は日本で発生するプレート内地震とは基本的に性質が異なるのであろうか。このような疑問が次々と湧いてきた。それにしても我々の観測結果はどのような新事実を明らかにしてくれるのであろうか。期待と不安の入り交じった気持ちにとらわれた。
帰国後、鋭意データの整理、解析を行なっているが全観測期間(2月27日〜3月6日)の結果を得るには今しばらく時間がかかりそうである。ここでは、とりあえず震源決定が済んだ2月28日21時〜3月1日03時までの6時間に発生した45個の余震の震源分布を紹介したい(余震分布図は前掲のホームページを参照)。余震は23.35°〜23.65°N、70.1°〜70.5 °E, および深さ10〜35kmの範囲に分布し、南北の断面で見ると全体的に傾斜角約40°の南傾斜の面が見える。余震の深さ分布から推測すると本震の主要なすべりは地殻の下部に存在し、断層は地表には突き抜けなかったと考えられる。断層が地表で観察されていないのはそのためであろう。USGSやHarvardの震源の震央はこの余震域のほぼ中央南側に位置する。地表で観察された地変の多くはこの余震域に含まれる場所で発生している。また、余震の分布は東西二つのグループに分かれており、その間に余震が発生していない領域が存在することも興味深い。予想では最終的に全観測期間で500個以上の余震の震源が決定されるものと見込まれ、より詳しい本震断層の位置、大きさ、およびその形状が明らかになることが期待される。
最後にこれは余震観測と直接関係がないことで一言。観測点の設置が一段落した後、我々は建物の被害および地表で観察される地変・液状化などの現場を見て回った。そうした中で、1819年に発生した地震でできたといわれるAllah Bund断層を探しに出かけることになった。この断層はパキスタンとの国境に近く、許可がないと外国人は立ち入りができない区域の中にある。3月4日、Bhujから3時間ほどかけてインド軍の関係者の案内でAllah Bund断層の現場に到着した。しかし、そこにはRann of Kachchhから続く平原が広がるだけで、断層崖のようなものは見られなかった。案内人の説明では遠くに見える軍の見張り櫓の下の部分が隠れて見えないのは、途中にある地面の隆起のせいであるという。数mもの落差の急な崖を想像していたものとっては、いささか拍子抜けの感じがした。持っていたGPSは24°07.024′N、69°15.644′Eの位置を示していた。この点を広島大学のMalik博士のホームページに掲載されていた活断層マップに落とすと、ほとんどAllah Bund断層の断層線に重なるので、断層の近くに居ることは間違いなかった。200年もの時間が経過し、侵食によってこのような地形になってしまったのであろうか。それとも、関係のない場所に案内されていたのであろうか。機会があれば再度出かけて確かめてみたい気がする。
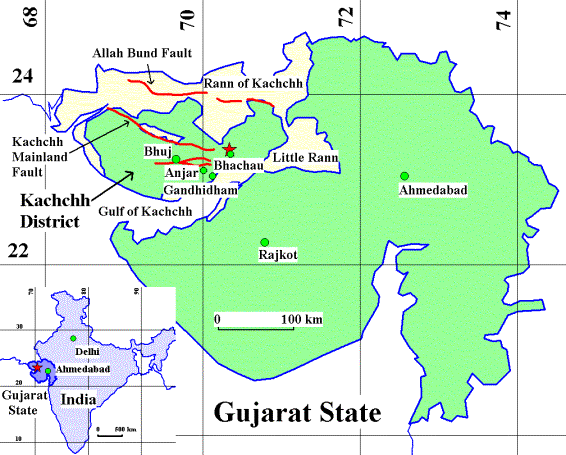
図1:Gujarat州・Kachchh地方の主要な都市及び活断層(星印はUSGSによる震源位置)